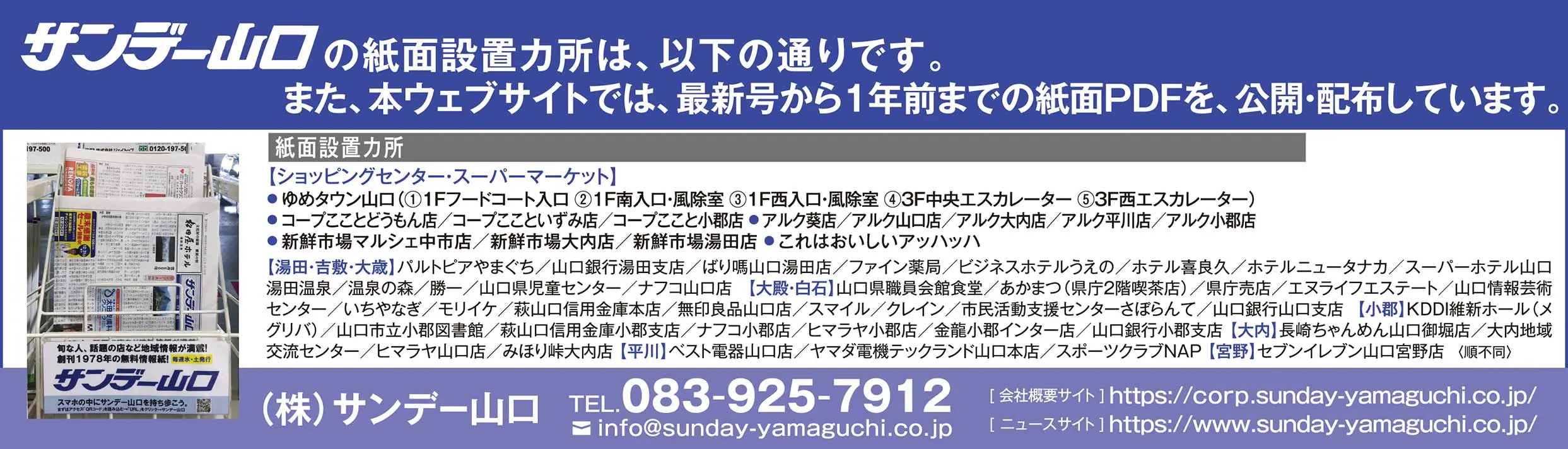先祖供養の大切な時期であると同時に、家族や親しい人たちと共に過ごすレジャーの要素も強くなっている「お盆」。本特集では、お盆の期間や由来についての説明と、家族や先祖を迎えるための準備に役立つサービスを提供している店舗や企業を紹介。迎盆準備の参考にしてみてはどうだろう。
お盆とは
お盆、正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれるこの行事は、古代インドのサンスクリット語「ウランバナ」の音を漢字にしたものと言われている。多くの場合、旧暦の7月15日を中心とし、7月13日から16日までの4日間を指すが、現在では新暦の8月13日から16日をお盆とする地域が一般的となっている。家族や親族が集まり、先祖や故人を偲ぶ時期として広く定着している。
お盆の過ごし方
お盆には「先祖の霊が自宅に帰ってくる」との考えから、13日は「迎え盆」、16日は「送り盆」と呼ばれている。盆提灯、故人の好物、そうめん、団子などを用意する地域も多い。
迎え盆までにはお墓参りを済ませ、仏壇を整えておこう。仏壇は柔らかい布でから拭きするのが基本だが、汚れがひどい場合はぬらした布で拭いてから、再度から拭きを行う。お墓についた汚れは、水を含ませたスポンジを使って汚れを落とし、最後に水をふき取るとよい。
永代供養墓や納骨堂を利用する際には、花や供物について施設が定めているルールを守るよう気をつけたい。
最近では「お墓を管理する人がいない」「足腰が弱りお墓参りが難しい」という悩みも増えている。家族が集まるこの時期は、墓石の汚れや破損の対処、墓じまい・移転・建て替えについて話し合うのに良い機会。お盆の風習は地域によってさまざまだが、「先祖を敬い、感謝する」という気持ちは共通だ。先祖や故人を偲び、日々に感謝しつつ、家族との時間を大切に過ごそう。

※電話番号のクリックで、各店舗・企業に電話をかけることができます。


 山口のニュース
山口のニュース

 前後の記事を読む
前後の記事を読む