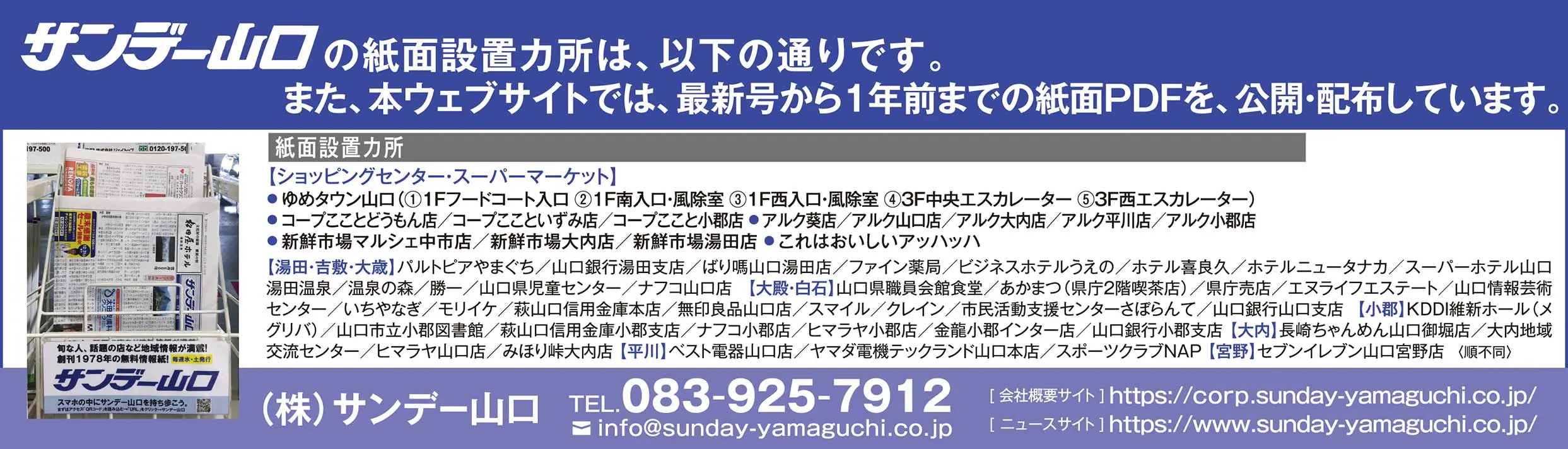大内氏がそのルーツを朝鮮半島百済国の第25代聖名王の第三皇子・琳聖太子としたことは有名な話である。琳聖太子は、西暦611年多々良の浜(防府市)に上陸し、聖徳太子に拝謁して大内の県(あがた)を安堵され、多々良の姓を賜って、この地に住み着いた。つまり朝鮮半島の王族の末裔と主張したのである。もちろん、今ではこれは大内氏の創作とされている。ただ、その発想は何ともユニークと言えるのではないか。何せ、当時はルーツと言えば、源氏か平家という時代だったのだから。
臨済宗の古刹・乗福寺には大内文化を花開かせた第24代弘世の墓があり、何とこの琳聖太子の供養塔と呼ばれるもの、また14世紀頃に製作されたと言われるカラフルな琳聖太子像もある。時代は異なるが、山口大学の開祖・上田鳳陽の墓もある。意外と知られていないのがこの寺のモミジ。春と秋には実に見事である。
文・イラスト=�古谷眞之助


 山口のニュース
山口のニュース

 前後の記事を読む
前後の記事を読む