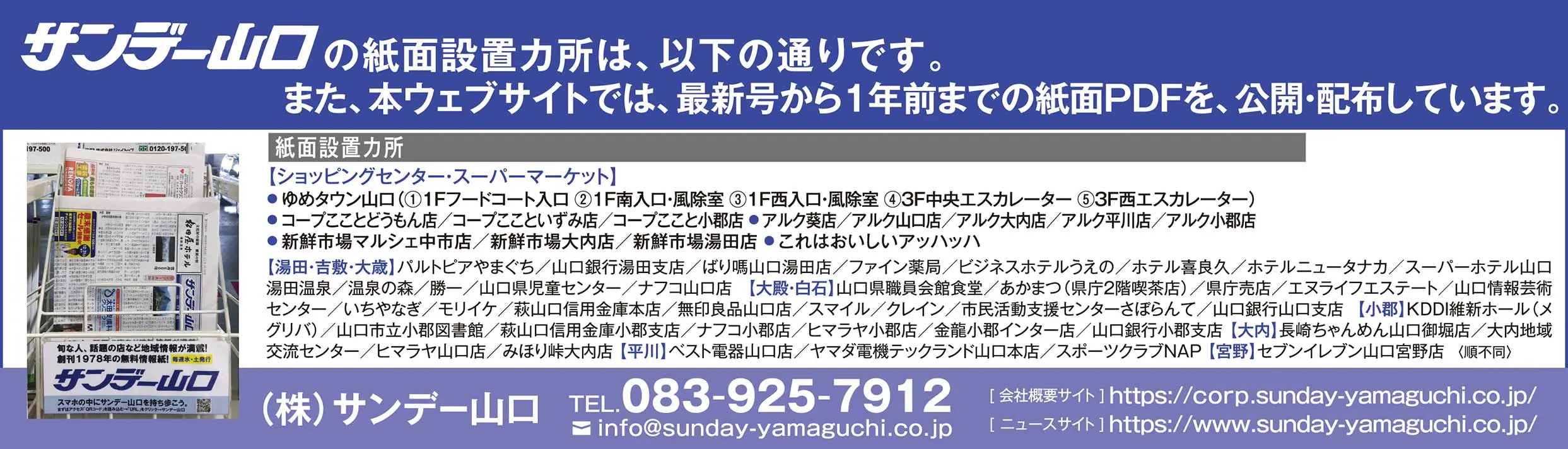「和の住まい推進リレーシンポジウムin山口」が、11月3日(月・祝)午後1時半から5時まで、KDDI維新ホール(山口市小郡令和1)で開かれる。「和の住まい推進関係省庁連絡会議」(文化庁、農林水産省、林野庁、経済産業省、国土交通省、観光庁で構成)協力の下、「山口県ゆとりある住生活推進協議会」が主催する。
伝統的な日本家屋には、瓦、土壁、縁側、続き間、畳、ふすまをはじめ、各地域の気候・風土・文化に根ざした空間・意匠、構法・材料など、「住まいづくり」の知恵が息づいている。だが近年は、こうした伝統的な住まいづくりとともに、そこから生み出された暮らしの文化も失われつつある。そこで、和の住まいや住文化の良さの再認識、伝統技能の継承と育成、伝統産業の振興・活性化等を図るため、2013年7月に「和の住まい推進関係省庁連絡会議」が立ち上げられた。その活動の一環として、毎年全国各地で「和の住まい推進リレーシンポジウム」は開催。山口県ではこれまで、初年度の2013年度、2020年度、2022年度の3回実施されており、今回が4回目となる。
当日はまず、国土交通省、文化庁、観光庁の各担当者が、「和の住まいに関する各省庁の施策について」報告。続いて、山口県土木建築部住宅課の山根昌浩課長が「山口県における空き家対策」について話し、住宅金融支援機構中国支店の担当者が「リノベーションに活用できるフラット35等の融資制度」を説明する。 そして、新建新聞社の三浦祐成社長による基調講演「空き家を生かし街を元気にする最新リノベーション手法」。空き家対策が急務となり法整備も進む中、民泊や店舗などの利活用によって地域活性化につながっている事例などを話す。三浦さんは、1972年山形県生まれ。信州大人文学部卒業後、長野市に本社を置く新建新聞社に入社。住宅専門紙「新建ハウジング」の立ち上げから記者を担当し、同紙編集長を経て現職に。ポリシーは「変えよう! ニッポンの家づくり」で、「住宅産業大予測」シリーズなどの執筆や講演多数。
定員は100人(先着)。聴講は無料だが、事務局の山口県建築士事務所協会への事前申し込みが必要だ。希望者はファクス(083-925-6763)またはメール(aak34230@pop21.odn.ne.jp)で、氏名、勤務先・学校名、住所、連絡先を伝えること。なお、当日CPD(継続職能研修)カードを持参した受講者には3単位が付与される。問い合わせは同会(TEL083-925-6701)へ。
主催者は「山口県では5軒に1軒が空き家となっており、今後も世帯数の減少による増加が予想される。だが、点在する空き家は、活用することで地域の『資源』に変わる。『実家が空き家になっている』といった人には、その利活用への大きなヒントがもらえると思う」と聴講を呼び掛けている。


 山口のニュース
山口のニュース

 前後の記事を読む
前後の記事を読む