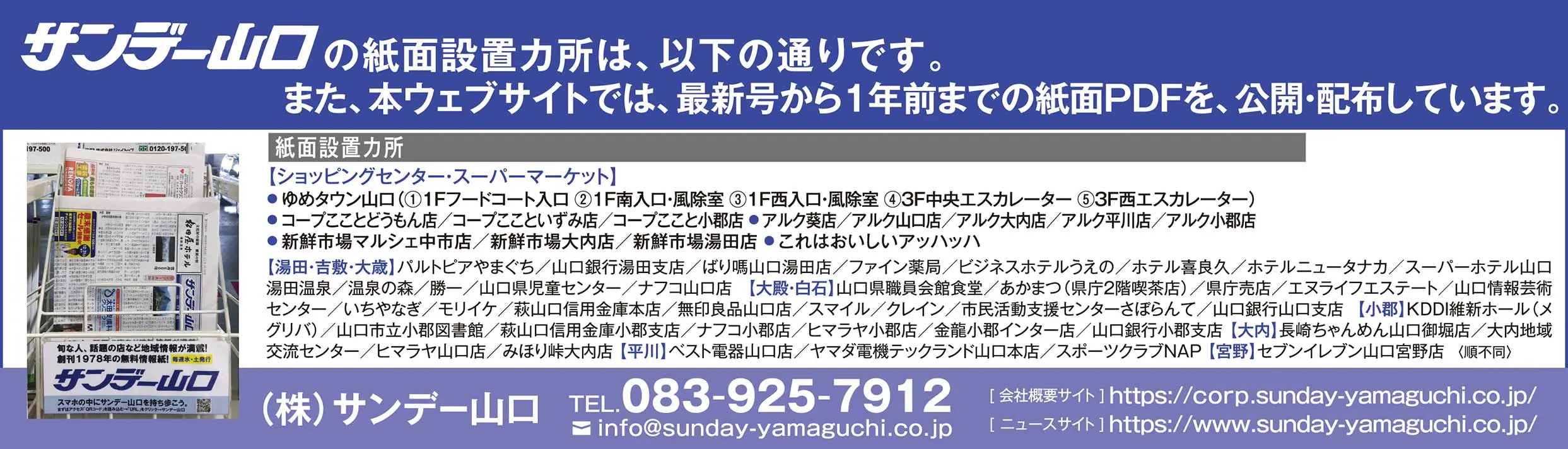平安時代に銭貨を鋳造していた官営機関「周防鋳銭司(すおうのじゅせんし)」は、825年(天長2年)4月、現在の山口市陶・鋳銭司地域に開設された。現地では、2016年度から山口市と山口大学が協働して発掘調査を続けており、新たな銭種を発見するなどの成果をあげている。そして、今年は設置1200年の節目の年に当たるため、同市は各種記念事業にも取り組んでいる。
その一つとして、9月27日(土)に記念講演会「みえてきた周防鋳銭司」を開催。会場は山口南総合センター(山口市名田島)で、時間は午後1時半から3時半まで。聴講は無料で、事前申し込みも不要。問い合わせは、同市教育委員会文化財保護課(TEL083-920-4111)へ。
最初に、同課の北島大輔主幹が「周防鋳銭司を描く」と題し、実際に現地で発掘に携わっている立場から基調報告をする。北島さんは日本考古学が専門で、島根県埋蔵文化財調査センター、鳥取県埋蔵文化財センターを経て現職。最新の発掘調査状況と、それを通して想像される銭貨鋳造工房について紹介する。
休憩をはさみ、山口大人文学部准教授で「史跡周防鋳銭司跡調査検討委員会」メンバーの黒羽亮太さんによる記念講演「鋳銭司時代の陶地域」。黒羽さんは、京都教育大教育学部と京大大学院文学研究科で学んだ後、阪大、京大、同志社大、立命館大などで講師を務めた。2020年から山口大で勤務しており、2024年4月から現職。周防鋳銭司の発掘調査では、木簡の破片等出土物の調査・分析も担当している。講演では、この地域の歴史的な特徴および鋳銭司が設置された背景について、日本古代史研究の立場から解説する。
主催者は「全国に数カ所しかなかった古代の造幣局が山口にあったことを多くの人に知ってもらいたい」と来場を呼び掛けている。


 山口のニュース
山口のニュース

 前後の記事を読む
前後の記事を読む